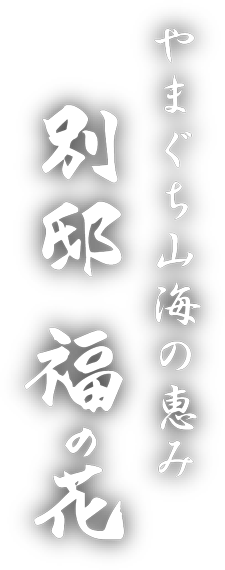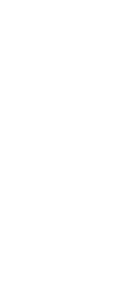【日本を代表する日本酒】山口地酒「獺祭」の造られ方〜上槽〜
長い時間をかけた仕込みが終わった後は、上槽という作業に入ります。
上槽というのは「搾り」とも言われ、簡単に言えばもろみからお酒を分離する作業です。
この搾りの状態によっても、お酒の味はかなり変わってきます。
昔は袋吊りという方法で上槽を行っていました。
現在でも昔ながらの方法で手間をかけて行っている酒蔵もあります。
しかし、機械化が進み、今では圧搾機という搾り機を使う酒蔵が増えてきています。
その流れの中で旭酒造では「遠心分離機」を導入しています。
これはフィルターを通さずに(物理的な衝撃が少なく)酒と酒粕を分けることができるため、酒の味に影響を与えることなく搾ることができるからです。
しかし、大量生産できないことが欠点としてあり、大量出荷の際には、圧搾機も併用し...
> 続きを見る