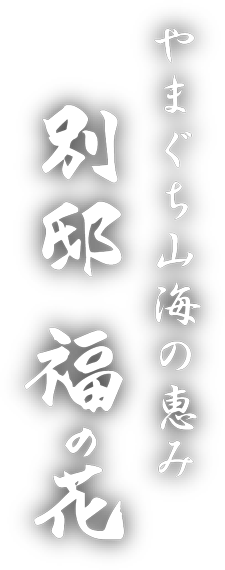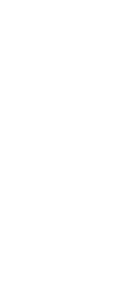2017/05/9 | 日本酒 「山口地酒の会」特集二十〜別邸福の花浜松町〜
2017/05/9 | 日本酒 「山口地酒の会」特集二十〜別邸福の花浜松町〜
こんにちは、別邸福の花です。
日本酒作りに欠かせない工程の1つに、「米を磨く」作業があります。
お米をどれだけ磨いたかを表す言葉は「精米歩合」と呼びます。ここでの数字は、「磨いた後に残っているお米の割合」となります。
大吟醸、吟醸など、長門峡の銘柄でも様々な種類が販売されていますが、その区別する1つの基準、精米歩合を今回は見てみましょう。

ちなみに、精米歩合100%はいわゆる「玄米」で全く削っていない状態、90%で白米の状態です。
80%、食用にも酒用にも向かない状態。
70%、すっきりとした飲み口のお酒になります。
60%、果物のような香りが出始めます。吟醸・純米吟醸酒の目安はここ。
50%、純米吟醸・大吟醸酒の目安。ちなみに、40%くらいまでは香りに変化はあるが、それ以上磨いてもあまり差は出てこないという意見もあります。
磨く技術が高ければ高いほど、香りの良い日本酒を作れる、ということ。現代では、精米歩合10%という驚愕の数字も登場しているとか。しかし、日本酒のおいしさの基準は香りだけではないので、様々な精米歩合のお酒を飲んでみて、違いを楽しむ飲み方も楽しいもの。肴も、味わいによって変わってくるでしょうしね。
 2016/10/28 | 日本酒 【山口の誇る地酒】別邸福の花浜松町が推す「雁木」(その一)
2016/10/28 | 日本酒 【山口の誇る地酒】別邸福の花浜松町が推す「雁木」(その一)
サクラが市花で、クスノキが市木、レンコン、白ヘビなどが有名で、
お城や観音水車でかまるくん、そして、錦帯橋という名所がある街…。
それが、山口県岩国市。
山口県の東部、広島県との県境にあります。中国地方の中心地である広島市までは約35kmという立地なので、広島のベッドタウンの役割も果たしています。
9つ穴があり「見通しが良い」と。縁起物で多く使われるのが「岩国れんこん」。
官民一体となって保護に取り組む「岩国の白ヘビ」は、国の天然記念物。
地元特産の杉で作られた、直径12メートルの「観音水車かまるくん」は、元日本一の水車だそう。
そして、市のHPのトップにも出てくる国の文化財、錦帯橋。

かつて城下町岩国を二分していた錦川をつなぐ「流されない橋」を目指して建てられたアーチ橋。そしてこの川は、瀬戸内海へ近つくと、
今津川と門前川という2つの川に分岐します。
その一方である、「今津川」のほとりに建つのが、今回の主人公、「雁木」を作る酒造「八百新酒造」です。ただひたすらに、
「純米酒」作りを続ける作り酒屋の歴史は、明治10年、この街から始まりました。
これから8回に渡り、日本酒「雁木」の周りにある様々なことを取り上げて、この一杯、この一本を紹介したいと思います。