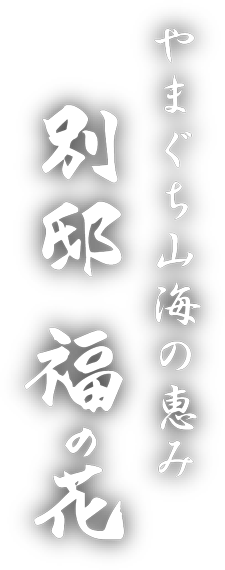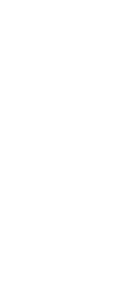こんにちは、別邸福の花です。
私たちは日常的に食べている主食は、ご飯にパン、そして麺があると思います。
今回の主人公のヒントは麺類。この麺の製法は昔々、中国から伝わってきたものでした。
鎌倉時代から始まるというその麺は、寺院用の食事よして広まり、まだ庶民が口にできる食事ではなかったそう。江戸時代になると一般市民にも流通するようになり、現代では夏の食事の定番。茹でるだけでなく炒め物などにもするようになりました。
前置きが長くなりましたが、今回の主人公は「そうめん」です。
こんにちは、別邸福の花です。
私たちは日常的に食べている主食は、ご飯にパン、そして麺があると思います。
今回の主人公のヒントは麺類。この麺の製法は昔々、中国から伝わってきたものでした。
鎌倉時代から始まるというその麺は、寺院用の食事よして広まり、まだ庶民が口にできる食事ではなかったそう。江戸時代になると一般市民にも流通するようになり、現代では夏の食事の定番。茹でるだけでなく炒め物などにもするようになりました。
前置きが長くなりましたが、今回の主人公は「そうめん」です。
下関市菊川で名産として名高い「菊川そうめん」は、下関ブランドの1つ。11回・2昼夜かけ手作業で引き伸ばされ、厳冬の空気にさらされる菊川のそうめん作り。市内でも自然豊かな盆地である菊川では、そうめん作りが昔から盛んに行われてきました。冬場の生産時期には、寒空の下で空気にさらされるそうめんの景色がみられるそう。そして夏本番を迎えるこの季節、私たちの食卓にあがる姿は「夏の旬」と言っても良いと感じます。
ちなみに、7月7日は七夕であると同時に、「そうめんの日」でもあります。中国では七夕の日に索餅を食べて病気を祓う習慣があり、その習慣が日本ではそうめんを食べることにつながっているそうです。夏真っ盛りの当日、いつもと少し違った気持でそうめんを食べてみたらいかがでしょうか。
10回に渡って行いました今回の「夏の旬」シリーズ。読んでくださった皆様に、少しでもこのテーマが知識となって伝わっていたらうれしいです。
それでは、またどこかで。ご精読、ありがとうございました。
http://www.soba-udongyoukai.com/info/2011/2011_0703_soumen.html
http://www.oidemase.or.jp/tourism-information/spots/10693
こんにちは、別邸福の花です。
私たちは日常的に食べている主食は、ご飯にパン、そして麺があると思います。
今回の主人公のヒントは麺類。この麺の製法は昔々、中国から伝わってきたものでした。
鎌倉時代から始まるというその麺は、寺院用の食事よして広まり、まだ庶民が口にできる食事ではなかったそう。江戸時代になると一般市民にも流通するようになり、現代では夏の食事の定番。茹でるだけでなく炒め物などにもするようになりました。
前置きが長くなりましたが、今回の主人公は「そうめん」です。
下関市菊川で名産として名高い「菊川そうめん」は、下関ブランドの1つ。11回・2昼夜かけ手作業で引き伸ばされ、厳冬の空気にさらされる菊川のそうめん作り。市内でも自然豊かな盆地である菊川では、そうめん作りが昔から盛んに行われてきました。冬場の生産時期には、寒空の下で空気にさらされるそうめんの景色がみられるそう。そして夏本番を迎えるこの季節、私たちの食卓にあがる姿は「夏の旬」と言っても良いと感じます。
ちなみに、7月7日は七夕であると同時に、「そうめんの日」でもあります。中国では七夕の日に索餅を食べて病気を祓う習慣があり、その習慣が日本ではそうめんを食べることにつながっているそうです。夏真っ盛りの当日、いつもと少し違った気持でそうめんを食べてみたらいかがでしょうか。
10回に渡って行いました今回の「夏の旬」シリーズ。読んでくださった皆様に、少しでもこのテーマが知識となって伝わっていたらうれしいです。
それでは、またどこかで。ご精読、ありがとうございました。

下関市菊川で名産として名高い「菊川そうめん」は、下関ブランドの1つ。11回・2昼夜かけ手作業で引き伸ばされ、厳冬の空気にさらされる菊川のそうめん作り。市内でも自然豊かな盆地である菊川では、そうめん作りが昔から盛んに行われてきました。冬場の生産時期には、寒空の下で空気にさらされるそうめんの景色がみられるそう。そして夏本番を迎えるこの季節、私たちの食卓にあがる姿は「夏の旬」と言っても良いと感じます。
ちなみに、7月7日は七夕であると同時に、「そうめんの日」でもあります。中国では七夕の日に索餅を食べて病気を祓う習慣があり、その習慣が日本ではそうめんを食べることにつながっているそうです。夏真っ盛りの当日、いつもと少し違った気持でそうめんを食べてみたらいかがでしょうか。
10回に渡って行いました今回の「夏の旬」シリーズ。読んでくださった皆様に、少しでもこのテーマが知識となって伝わっていたらうれしいです。
それでは、またどこかで。ご精読、ありがとうございました。
http://www.soba-udongyoukai.com/info/2011/2011_0703_soumen.html
http://www.oidemase.or.jp/tourism-information/spots/10693
2017/05/24 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編 特集九~別邸福の花浜松町
こんにちは、別邸福の花です。
今回の主人公は、山口県に夏の到来を伝える「ウニ」。山口県とウニのつながりは遠い昔の縄文時代から確認されています。下関市の縄文遺跡、「潮待貝塚」からは、約2000年前のウニの殻が発見されているそう。そんな山口県産のウニは、海女さんらの手により、6~8月、夏の季節に収穫されます。

海の幸が収穫されるところには、保存技術も産声をあげるもの。山口県の名産品の1つに、「アルコール漬け瓶詰めウニ」という食べ物があります。ちょっとした偶然からこの加工技術は誕生しました。
下関市には六連島という島があります。明治時代、捕鯨船の停泊地だったこの島には、多くの外国人がやってきたそう。人が集まり、うまい食事があれば、宴の席が自然発生するのはどの時代どの場所も一緒。その席で出されていたウニに偶然こぼれたのが度数の高いウオッカ。そして、周囲も酔っていたのでしょうか。そのウニを口にしたところ、「たいへん美味である」と太鼓判が押され、この加工技術の歩みが始まりました。
その後、保存に適切なアルコールの種類やその製造方法が確立されました。同時に、高級食材のウニを活かすために瓶を使用したりと、現在に至る様々な工夫が行われてきました。
もちろん、生のまま食べるのも美味しい山口のうに。ここ下関で収穫されるうにには、生と酒漬け、2つの楽しみ方があるのですね。
http://uni.or.jp/products/history
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/kanko/bussan/03suisan-g.html
2017/05/23 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編 特集八~別邸福の花浜松町~
こんにちは、別邸 福の花です。
「魂消る」という言葉があります。読み方は「たまげる」。魂が消えるほどの思いから、「驚き」という意味で使われる言葉です。もともとは「魂消る(たまきる)」という言葉で、その意味は「怯える」で使われ始めたのは鎌倉時代。その後、室町時代に今も使われる意味に変化していったそうです。
時を経て今は21世紀。山口県の日本海側、萩や長門ではこの「魂消る」という言葉を用いた、とある農作物があります。それが、今回の主人公、「萩たまげなす」です。

どんなところに魂消るかといいますと、それはその大きさ。
長さは約30センチメートル、重さは500グラム以上、スーパーなどに売っている普通のナス3~4本分の大きさを誇ります。見た目だけじゃないのがそのおいしさ。甘い皮に、しっかりとつまった実、きめ細かな肉質。また、ナスの中でも糖質が高い一品です。ナス料理の定番、焼きなすやお浸し、和洋中・調理法問わず味わうことのできる存在感に、魂消ること間違いないでしょう。
そんな「萩たまげなす」の始まりは昭和初期。その原点は長門市で栽培されていた「田屋ナス」という品種です。その後、おとなり萩市へ種が伝わり、栽培が始まったとのこと。いったん栽培が滞る時期もありましたが、平成15年に復活した歴史を持ちます。
百聞は一見に如かず。少しでも興味を持っていただけたら、実際に見て食べてみて、「魂消る」瞬間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
http://shinsenichiba-yamaguchi.jp/%e8%90%a9%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%92%e3%81%aa%e3%81%99/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/kanko/bussan/01nousan-y.html
2017/05/22 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編 特集七~別邸福の花浜松町
こんにちは、別邸福の花です。
これまで、グルっと山口県を一周してきたところ。ここからは、海の幸を離れて山の幸へ行ってみましょう。思いのほか、海の幸編で盛り上がってしまったもので。
時は幕末、アメリカから日本にとある野菜が入ってきました。その野菜は、断面が星形だったり、五角形だったり、独特の歯ごたえに粘りのある食感。ここまできたら何の野菜かおわかりでしょう、今回はオクラが主人公です。

その中でも、山口県がテーマなので、長門市で主に栽培されているという、白オクラを紹介したいと思います。一般的なオクラよりも白くすき通った身は、その名のとおり。普通のオクラに比べて粘りが3倍強くアクが少ないことから、生食に最適。別名、「サラダオクラ」とも呼ばれる品種でもあります。
山口県と白オクラの出会いは戦後。引き揚げてきた元兵士が持ち帰ったといわれ、60年ほど前から栽培が始まったそう。このオクラ最大の弱点は、生産に時間がかかること。花が咲いた後、花を回収する作業などは全部手作業。もし怠ってしまったら、身が黒くなったり、枯れてしまうことも。そんな貴重なオクラを守るため、長門市でも行政・民間と知恵を出し合って、このオクラの生産者を保護して、そこから全国展開しようという動きも広がりつつあるようです。
どんな食べ物にもある、生産者など人の背景。一本のオクラに込められたそんな人たちの物語を知ってみるのも、旬を楽しむ1つの方法かもしれません。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/kanko/bussan/01nousan-y.html#sanchimap
http://www.yasainavi.com/zukan/okra.htm
2017/05/21 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編 特集編六~別邸福の花浜松町~
こんにちは、別邸福の花です。
別名「香魚」、その魚は、火をくべて焼き色を付けて食べると、清涼感あふれる風味と共に初夏の訪れを伝えてくれます。
そんなお魚は「アユ」。今回は海から少し離れて内陸の川から旬の味をお届けします。
山口県だと、県内佐波川などで釣り上げることのできるアユ。縄張りを作る習性があるので、真上から釣り糸をたらし、縄張りを荒らす侵入者に対抗する形で釣り上げるそう。
そうして釣り上げたアユの代表的な食べ方は、やっぱり塩焼き。鱗や骨など、魚を食べる時に気になる部分が細かく柔らかいのが特徴なので、串に刺したまま豪快にかぶりつけるのも魅力の1つでしょう。

山の中で収穫できる数少ない魚からでしょうか。様々な地域で保存食として、現在も郷土料理として残っているアユ。山口のお隣島根県益田などでは、アユの内臓を塩辛にした食べ物、「にがうるか」というもがあります。日本酒に合いそうな肴です。また、他の地域では天日干しなどの食べ方も見られます。
「清流の女王」と呼ばれるアユは、色あせていない黄金色の個体がおすすめ。漁獲された川によって異なるという香りを食べながら楽しんでみてはいかがでしょう。
http://www.jf-ymg.or.jp/zukan/ayu.htm
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%A6
2017/05/20 | 未分類 山口に夏の旬‐食べ物編特集五~別邸福の花浜松町~
こんにちは、別邸福の花です。
前回に引き続き日本海の海の幸をご紹介します。
45秒・時速70キロ・100~200メートル
当ブログではあまり使ったことのない、早さを表現するこれらの数字。
この3つに共通する魚が、夏場の日本海をにぎわせます。
それが、今回の主人公、トビウオ。

推定45秒間、時速70キロメートルで、平均して100~200メートルの距離を水中から離れて飛ぶお魚。さらに、海面から10メートルほどの高さまで飛び上がることもできます。
その体は、「飛ぶ」ことに特化しています。食べた餌を早く体外に出すための排出器官をもっており、体を常に軽くできる特殊な設計のその体には胃がないそう。このような体になったのは、外敵から身を守るためとのこと。
たんぱくな白身のお刺身は、そんな運動量の多さと無駄な脂肪などを蓄えない体質からきているのでしょう。たたきやなめろうなどの食べ方もおいしいそうです。
脂肪含有量がわずか1パーセントという特性を活かして、ひもの作りの原料にも重宝するとびうお。一方でたんぱく質の量が多く、干している間に熟成がすすむのもポイント。山口県ではありませんが、有名なくさやの原料にもなりそうです。
幼いころ、空を飛ぶ魚として子供心をくすぐったトビウオ。その生態を知ると、食べる時もよりおいしく感じられそうですね。
http://www.maruha-shinko.co.jp/uodas/syun/27-tobiuo.html
http://www.jf-ymg.or.jp/zukan/tobiuo.htm
2017/05/19 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編 特集四~別邸福の花浜松町~
こんにちは、別邸福の花です。
全国各地で地元商品のブランド化が積極的に行われる今日このごろ。
山口県でも、「やまぐちブランド」という制度があります。
これは、山口県農林水産物需要拡大協議会が設けているもので、県内で生産される農林水産物および主な原材料が山口県産100パーセントの加工品を解消に、味や品質を重視した独自の基準を設けて厳選して、県内外へ積極的に発信するブランドのこと。
現在、79の商品が登録されています。前置きが長くなりましたが、今回の主人公はここに登録されている8種類の水産物の1つ、「いさき」です。とれる海域は日本海です。

主な生息地は東北より南で水深100メートルほどの場所に生息。夜行性で夜になると餌を求めて浮かび上がるのを一本釣りしたりしています。主な漁場は日本海側、萩市や長門市。平成24年には、全国で漁獲高が2位になったことも。・
漁獲高の高い長門市仙崎では、とれたてのイサキを背開きにしたあと、一夜干しして食べるのが産地ならではのおいしさ。元々は漁師の家庭料理だというこの食べ方。作るとき、のど元がオレンジ色に染まっているのが旬のサインだそう。また、皮がおいしいとのこと。やまぐちブランドの認定基準にも皮が整っているかも含まれているので納得です。
もちろん旬はどんな食べ方でもオッケー。せっかく食べるのだから、様々な食べ方で旬のイサキを楽しみたいところですね。
http://www.senzakisakana.com/category/shokutext/pdf/haru/isaki.pdf
http://www.buchiuma-y.net/brand/suisan/isaki.html
http://www.jf-ymg.or.jp/zukan/isaki.htm
2017/05/18 | 未分類 山口の夏の旬‐食べ物編ー特集二~別邸福の花浜松町~
こんにちは、別邸福の花です。
標高8848メートル、世界最高峰の山エベレスト。
水深10911メートル、世界で最も深いマリアナ海溝の最深部。
世界最大の動物はシロナガスクジラ。
いつもとは少し違う書き方で、「世界一」を書いてみました。実は今回紹介する夏の旬は、少しだけですが、世界一を噛んでいるお魚さんです。

「スズキ目」
魚類だけでなく脊椎動物の中で、最も多くの種類を数える「目」の代表魚の1つが、今回紹介する「スズキ」です。私たち日本人に「鈴木」の名字が多いのと同じように、お魚の世界でも大所帯なのは何かの偶然でしょうか。前置きが長くなりましたが、瀬戸内海側西部で見られます。
成長するにつれて名前が変わる出世魚なスズキ。淡白な白い身は、「すすぎ洗いしたようなきれいな身」に由来するほど。
そんなスズキの食べ方は、「洗い」はいかがでしょうか。いったんさばいて食べやすいサイズに切り分けたスズキを氷水で締め、さらに水の勢いで余計な油をそぎ落とす食べ方です。2つの過程を通ることで、臭みのない白身魚の味を活かした料理になります。
ほかにも、洋風ならムニエルなど白身魚の定番として様々な食べ方ができるスズキ。
お酒の肴としても、少しさっぱりとした一杯と一緒にどうぞ。
 2017/05/17 | 未分類 「山口地酒の会」特集二十七〜別邸福の花浜松町〜
2017/05/17 | 未分類 「山口地酒の会」特集二十七〜別邸福の花浜松町〜
こんにちは、別邸福の花です。
季節の長門峡シリーズも最後の2季節、秋と冬を迎えました。
ひやおろし、熱燗、お酒の席で日本酒が注目される季節がやってきました。
岡崎酒造場が展開するのは、ひやおろしの「秋熟」です。
まずはひやおろしの何たるかから始めましょう。冬に搾った日本酒は品質を保持するため一度火入れします。その後、夏を越えて外気とタンク内の温度が同じくらいになった時、再び火入れせず卸すことから名付けられた「ひやおろし」。夏場はタンク内で熟成が進むことで、より深い味わいとなって私たちの前に注がれます。

ちなみに、二回目の火入れをしないのはその風味や味わいを守るため。「夏を越す」というのが大事なキーワードになるひやおろし。ひと夏の期間で育まれた「おいしさ」を楽しめるのは、こういう段階を踏んでいるからなのですね。
「秋熟」は2種類。吟醸は芳香な香りとキレのある味わい。純米酒ではまろやかさが加わっています。どちらも日本酒度は+なので端麗な辛口に仕上がっています。
日本酒の、長門峡の熟成を味わえるひやおろしは、ちょっと肌寒くなってきた時期にぜひ楽しんで欲しい一杯だと思います。
長らく続きました、長門峡シリーズも今回が最終回。
同時に、今回のイベントに登場する3種類の紹介記事がこれにて終了になります。
長い間ご愛読、ありがとうございました。続きはぜひ、イベント会場で皆さまの舌と雰囲気で味わってください。今後とも「別邸 福の花」をよろしくお願いします。
 2017/05/17 | 未分類 「山口地酒の会」特集二十六〜別邸福の花浜松町〜
2017/05/17 | 未分類 「山口地酒の会」特集二十六〜別邸福の花浜松町〜
こんにちは、別邸福の花です。
長門峡の季節シリーズを今回もお届けしたいと思います。
ところで皆さま、これから来る暑い夏、飲んでみたいお酒って何でしょうか?
ビールにサワー、炭酸のきいた「のどごし」を楽しめるお酒が頭に浮かぶと思います。
一方で、日本酒、は出てくるでしょうか。実のところ、夏の日本酒は昔、あまり売れていなかったという話を耳にしました。でも今は、各酒蔵から「夏酒」と銘打った日本酒が販売され、「夏こそ日本酒を!」という動きが活発になっているようです。

その味わいは、青を基調とした「夏」の鮮やかさを感じさせる仕上がりです。
後味がすっきりとした味わい、時に氷を入れてオンザロックなんて飲み方も楽しめます。
「長門峡」の夏酒は、低アルコールでスッキリとした味わい、爽快感と夏を感じさせる言葉で表現される味わい。青色のビンがその印象を後押しします。
長門峡だけでなく、「日本名酒協会」も注目する夏酒の動き。
昨年、「The夏酒」シリーズと銘打ったキャンペーンを開催しています。
夏らしい味わいに加えて、従来から夏場におすすめしてきた「夏の生酒」に新たな要素を追加しました。それが、「常温でも保存できる」ということ。「冷蔵庫に入らない」というお客様の声を参考にしました。各酒蔵、夏を意識した素敵なラベルも魅力的。
これからの季節、そんな「夏」を意識した日本酒を片手に夏らしいこと、してみてはいかがですか?
< PREVNEXT >